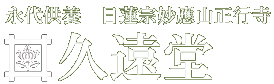 |
||||||||||||
|

当山は日蓮宗の寺院ですが、その日蓮宗では宗祖日蓮大聖人が定めた曼荼羅を以て本尊と定めています。 当山本堂の内陣(左写真)は、この曼荼羅本尊に則り、日蓮大聖人を中心として周囲に諸仏諸尊を配置。立体曼荼羅の小宇宙を構成しています。 (写真上にマウスのカーソルを乗せると、諸仏諸尊の名が表示されます)
鎌倉時代の貞応元年(1222年)、房州小湊(現千葉県鴨川市)に漁師の子として生まれた善日麿少年は、清澄寺にて出家。その後、比叡山、高野山への遊学の中で『法華経』を最も尊い経典と仰ぐに至って自ら「日蓮」と号し、建長五年(西暦1253年)4月28日、清澄山の旭ヶ森へと登り、遙か太平洋の水平線から昇る朝日に向かって「南無妙法蓮華経」の御題目を初めて唱え、この世の浄土実現を誓願、日蓮宗を立教開宗されました。
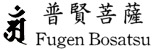 普賢菩薩は梵語(サンスクリット語)で「サマンタ・バダラ(समन्तभद्र)」と言い、世界に普く現れ仏の慈悲と理知を顕して人々を救う賢者とされる所から、日本では原語を意訳して「普賢菩薩」と呼んでいます。 普賢菩薩は、六牙の白象の背中の蓮華座に結跏趺坐して合掌したり、宝剣、五鈷鈴、五鈷杵、如意宝珠、蓮華、経典を持つ等、その姿は様々です。(当山の像は両手で蓮華の茎を持っています)
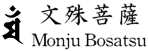 文殊菩薩は梵語(サンスクリット語)で「マンジュシュリー(मञ्जुश्री)」又は「マンジュゴーシャ(मञ्जुघोष)」と言い、日本では「文殊師利菩薩」、略して「文殊菩薩」と呼ばれています。又、原語を意訳して「妙吉祥菩薩」、「妙徳菩薩」、「妙首菩薩」等とも呼ばれます。 文殊菩薩は、獅子の背中の蓮華座に結跏趺坐し、右手に智慧を象徴する利剣(宝剣)、左手に経典を乗せた青蓮華を持ち、「智慧の仏様」として尊崇されています。(当山の像は右手は欠損、左手には経典を持っており、普賢菩薩と共に日蓮大聖人と三尊を構成しています)
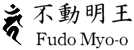 不動明王は梵語(サンスクリット語)で「アチャラ・ナータ(अचलनाथ)」(動かざる守護者)と言い、密教の教主・大日如来の化身とされ、密教特有の尊格である五大明王の主尊でもあります。又、目黒不動・高幡不動などでも知られる様に、古くから人々の信仰対象とされてきました。 不動明王は、元来、密教特有の仏尊ですが、天台宗の比叡山、真言宗の高野山に遊学経験のあった日蓮大聖人が曼荼羅本尊に愛染明王と共に取り込んだ事から、日蓮宗の寺院の中には当山の様に祀っている所もあります。
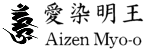 愛染明王は梵語(サンスクリット語)で「ラーガ・ラージャ(रागराज)」(赤い王)と言い、人間の本能である煩悩と愛欲を向上心に変えて仏道を歩ませる功徳があります。又、三眼六臂(三つの目と六本の腕)の異形でありながら、恋愛・縁結び・家庭円満を司る所から、古くより人々の信仰対象とされてきました。 愛染明王は、不動明王と共に日蓮大聖人が曼荼羅本尊に取り込んだ密教特有の仏尊ですが、「生死即涅槃」を表す不動明王に対して、「煩悩即菩提」を表すとされています。
毘沙門天は梵語(サンスクリット語)で「ヴァイシュラヴァナ(वैश्रवण)」(よく聞く所の者)と言い、日本では原語を意訳して「多聞天」と呼んで、持国天(東方)・広目天(西方)・増長天(南方)と共に四天王を構成、仏教世界の北方を守護する守護神の一人に数えられています。 又、四天王とは別に単独で祀られる際には、原語の音に近い「毘沙門天」と呼ばれ、戦国時代、甲斐の武田信玄の最大の好敵手として、信州川中島で死闘を繰り広げた越後の上杉謙信が篤く信仰していた事でも有名です。
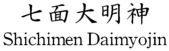 七面大明神は、吉祥天、弁才天、或いは『法華経提婆達多品第十二』に登場する龍女 伝説によると、身延山 爾来
大黒天は梵語(サンスクリット語)で「マハー・カーラ(महाकाल)」(大いなる闇黒 日本では原語を意訳した「大黒天」、又は「摩訶
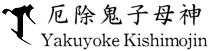 鬼子母神 鬼子母神は、500人とも千人とも1万人とも言われる多くの子供がいながら、他人の子供を捕
毘沙門天・鬼子母神と共に『法華経陀羅尼品
金剛力士 口を開いた阿形
当山に於いても、平成29年、山門を立て替えたのを機に、新たに二体一対の金剛力士像を奉安し、向かって右側の阿形像(上写真)を「理徳金剛
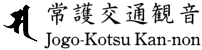 観世音 観音菩薩は「普門示現
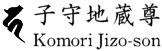 地蔵菩薩は梵語(サンスクリット語)で「クシィティ・ガルヴァ क्षितिघर्भ」(大地の胎内 地蔵菩薩は他の菩薩が宝冠を戴
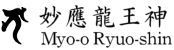 『法華経序品 当山境内 |
|||||||||||
| Copyright© 2008-2018. Shōgyō-ji KUONDŌ All Rights Reserved. Produced by Website Creation Studio web-shi TAKESHITA. |
||||||||||||















